インドの食卓に欠かせないスパイス「ターメリック」。その主成分クルクミンには、炎症を抑えがんを防ぐ可能性が注目されています。
臨床研究と食べ方のポイントを紹介します。
ターメリックが注目される理由
インドやスリランカでは、古くからターメリック(ウコン)が「薬草スパイス」として使われてきました。黄金色の粉末は、カレーや豆料理に欠かせず、アーユルヴェーダでは「自然の抗炎症ハーブ」と呼ばれています。
主成分のクルクミン(Curcumin)には、次のような働きが知られています。
-
強力な抗酸化作用
-
NF-κB・COX-2などの炎症経路の抑制
-
がん細胞の増殖抑制・血管新生の抑制
これらの作用により、慢性炎症を鎮め、生活習慣病やがんの予防に役立つ可能性が研究で示されています。
がんは“炎症の病気”でもある
「がん=細胞の異常増殖」という理解は一般的ですが、
実は、がんは長期的な炎症反応の結果として生まれる病気でもあります。
体内で炎症が長く続くと、
-
DNAの損傷
-
活性酸素の増加
-
新しい血管の異常増殖
が起こり、これが腫瘍形成の土壌となります。
クルクミンはこれらの炎症連鎖を抑えることで、
がんの進行や再発を防ぐ自然なサポート役になる可能性があるのです。
臨床研究で示されたクルクミンの可能性
| 効果対象 | 主な研究報告 | 結果概要 |
|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | Clin Gastroenterol Hepatol, 2006 | クルクミン摂取群で再発率が有意に低下。 |
| 結腸ポリープ | Cancer Prev Res, 2011 | ポリープ数が減少傾向を示す。 |
| 乳がん細胞モデル | Breast Cancer Res Treat, 2013 | アポトーシス誘導・NF-κB経路抑制を確認。 |
| 炎症全般 | J Inflamm Res, 2015 | 慢性疼痛・炎症マーカー(CRP)の減少を報告。 |
こうしたデータからも、クルクミンは「炎症性疾患の自然な調整因子」として注目されています。
効果を高める食べ方のコツ
クルクミンはそのままだと吸収率が低いため、調理法を工夫することが大切です。
-
油と一緒に摂る:脂溶性のため、オイル調理で吸収UP
-
黒胡椒(ピペリン)を加える:吸収率を最大2000%上げる報告あり
-
加熱しすぎない:風味と有効成分を保つため、調理終盤に加えるのがおすすめ
例:
ターメリック+黒胡椒+オリーブオイルを使った温野菜、豆カレー、スープなど。

インドではなぜがんが少ないのか?
世界がん研究基金(WCRF)の統計によると、
インドの結腸がん発症率は欧米の約5分の1〜10分の1。
その理由として、
-
スパイス中心の抗炎症的食文化
-
野菜と豆中心の食事
-
動物性脂肪が少ない食習慣
などが挙げられます。
このような「自然と炎症を抑える暮らし」が、
がんの発生リスクを低下させていると考えられています。
まとめ:食卓でできる小さな予防医学
ターメリックは、私たちの日常の食卓で実践できる抗炎症ケアのハーブです。
がんを「炎症の延長線上の病気」ととらえ、クルクミンの力を食事の中に取り入れることが、身体を守るシンプルなセルフケアになります。
参考文献
-
Chevalier G, et al. J Environ Public Health, 2012
-
Brown D, Chevalier G. J Altern Complement Med, 2010
-
Oschman JL, et al. J Inflamm Res, 2015
-
Aggarwal BB, Harikumar KB. Anticancer Res, 2009
その他
次回は秋から冬におこなう夏のダメージケアをお届けできるかも?日常のセルフケアについてもお楽しみに



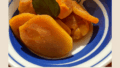
コメント