ベランダで迎えた小さな収穫
ベランダで育てているハーブや薬味たちが、夏の日差しを浴びて元気に育ちました。先日ついに、待ちに待った収穫のとき。ハート型の器にたっぷり入った黒い果実、みずみずしいミョウガ、そして香り豊かな緑の葉──。
その緑の葉こそ、スリランカでは「カラピンチャ」、インドでは「カレーリーフ」と呼ばれる植物です。収穫したばかりの素材をお皿に盛ってみると、自然からの贈り物をそのままいただくような、満ち足りた気持ちになります。
名前は違っても同じ植物
「カラピンチャ」と「カレーリーフ」は、どちらも Murraya koenigii というミカン科の植物。呼び名が異なるだけで同じものです。
-
スリランカ:カラピンチャ(කරාපිංචා)
-
インド:カレーリーフ(Curry Leaf)
日本では「カレーリーフ」として広まっていますが、スリランカ料理に触れると「カラピンチャ」という呼び名に親しみを持つ方も多いでしょう。
同じ植物でも、地域や文化によって呼び方が変わるのはとても興味深いことです。
スリランカ料理に欠かせない香り
スリランカでは、カラピンチャは料理に欠かせないハーブです。豆カレーや野菜カレーを作るとき、まず油に葉を入れて炒め、香りを引き出す「テンパリング」を行います。数枚の葉を油に落とすと、爽やかな香りが広がり、料理全体に深みが増します。日本の台所でも、煮物や炒め物にさっと加えると「どこか南国の風を感じる味」に変わります。

まだ緑の実をつけている株。これが黒いルビーのようになります
黒い果実の楽しみ方
今回の収穫では、黒々とした果実も手に入りました。艶やかで宝石のような姿は、ジャムーン(ジャワプラム)にも似ています。
-
生食:ジューシーで甘く、爽やかな酸味が広がる
-
ジャム:煮詰めると深い紫色になり、甘酸っぱさが際立つ。トーストやヨーグルトにぴったり
-
発芽:食べた後の種から芽が出て、苗を育てる楽しみもある
食べて美味しいだけでなく、次の命へとつなげる喜びまで与えてくれるのは、自然の大きな恵みだと感じます。
ミョウガと日本の夏
一緒に収穫したミョウガは、日本の夏の定番。薬味にすれば食欲を引き出し、炒め物や味噌汁に加えても爽やかな香りを楽しめます。庭の片隅で採れたものは特に新鮮で、採りたての香りが格別です。

お口の中に種が残ります。それを植えて株を増やしますが、時に、実が落ちてそのまま発芽することもあります。
アーユルヴェーダ的な効能と食医療
アーユルヴェーダの視点から見ると、今回の収穫物はどれも暮らしを整える“自然の薬”です。
カラピンチャ(カレーリーフ)
-
消化力(アグニ)を整える
-
消化不良や便秘を改善する
-
血糖値の安定に役立つ
-
髪や肌を健やかに保つ
料理だけでなく、お茶やスープとしても利用されます。
-
カラピンチャティー:乾燥葉を煮出すと爽やかな香り。食後に飲むと消化を助ける
-
カラピンチャスープ:胃腸を休めたいときにぴったり。葉を煮出して塩で整えるだけで、優しい味わいに
黒い果実(ジャムーン/ジャワプラム)
-
体を冷やし、夏の熱を鎮める
-
糖代謝を整えるとされ、糖尿ケアに用いられる
-
消化を助け、口内を爽やかに保つ
-
種も乾燥させ粉末にし、薬効として利用されることがある
ミョウガ
-
食欲を高め、消化を促す
-
夏のだるさを和らげる
-
体内の余分な湿気を取り除く
和とアーユルヴェーダの視点が出会うと、身近な植物の力がさらに輝いて見えてきます。
暮らしに取り入れるセルフケア
-
食後にカラピンチャティーを飲んで消化をサポート
-
朝にジャムーンを食べて、体をクールダウン
-
夜はミョウガを薬味にしたカラピンチャスープでリセット
ベランダで育てた植物や果実を「食べて癒す」「飲んで整える」ことで、アーユルヴェーダのセルフケアが自然に暮らしに根づいていきます。
小さな収穫がくれる大きな学び
お庭やベランダでの栽培、ガーデニングは、ただ食材を得る以上の学びをくれます。葉を摘むときの香り、実を収穫するときの手応え、雨上がりの葉のきらめき──。スリランカでは「カラピンチャ」、インドでは「カレーリーフ」。名前は違っても、植物の力強さは同じ。文化を越えて受け継がれてきた知恵が、私たちの食卓にも生きています。

フレッシュのカレーリーフはカレー作りに欠かせない!香りがちがうのです。
まとめ
今回の収穫で感じたのは、「植物は食材であり、薬であり、そして暮らしを豊かにする存在」ということ。皆さんの身近には、どんなハーブや果実がありますか?ぜひ育て、食べ、そして癒しとして取り入れてみてください。

根元に増えた!
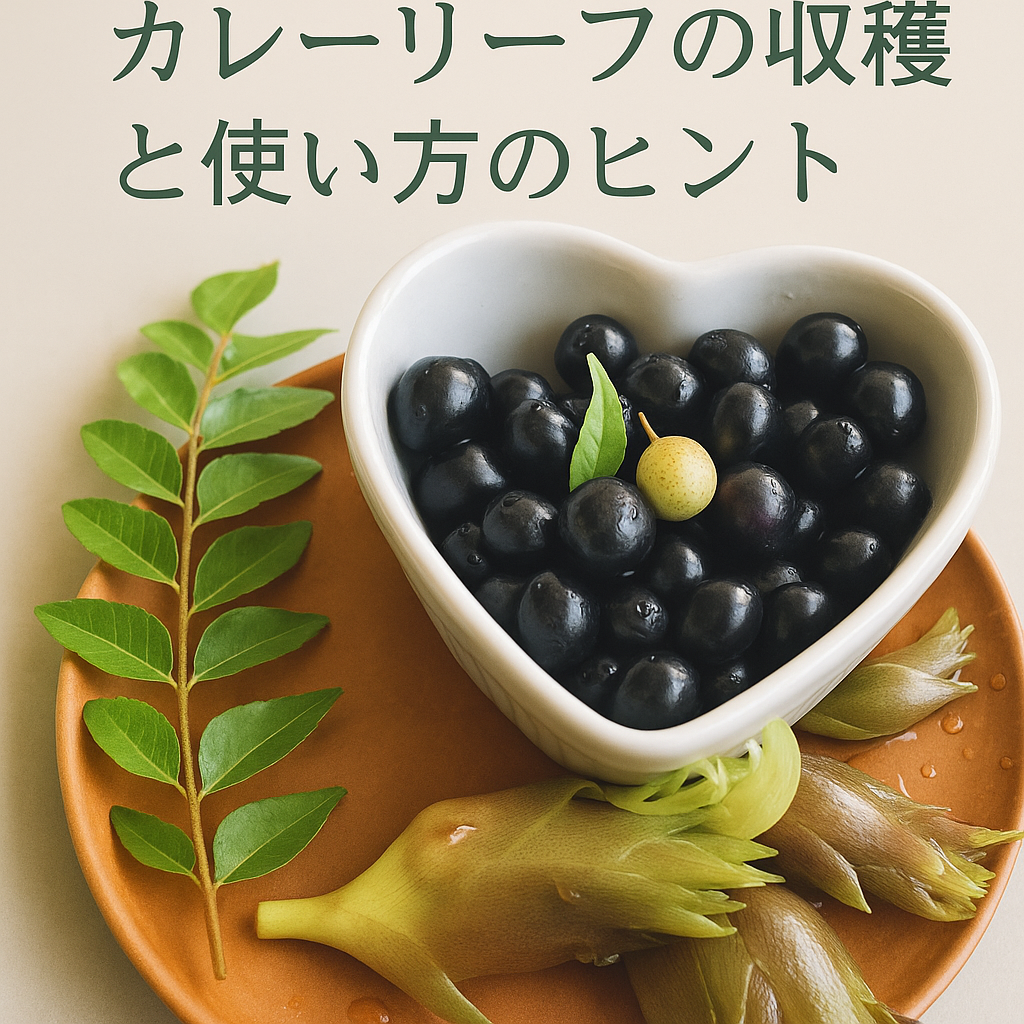


コメント